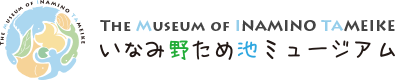ため池の水草
ため池と水草
ため池や河川などの水域に生育する植物たちを水草(水生植物)と呼んでいます。兵庫県内には約120種の水草の生育が確認されていますが、ひとつの県にこれだけの種類の水草がみられる例は多くありません。兵庫県の水草がこれほど豊かなのは、さまざまな環境のため池が、数多く存在するからにほかなりません。ため池に見られる水草だけで約90種類を数えます。
水草の生育形
水辺の浅い場所には、ヨシやマコモのように茎や葉が水面上に出る抽水植物が生えています。ヒシやジュンサイのように葉を水面に浮かべているのは浮葉植物です。一生を水中に沈んだままで暮らすクロモやオオトリゲモなどの「藻」は、沈水植物と呼ばれます。ホテイアオイやウキクサのように根を張らず水面に浮いているのは浮遊植物です。
葉は水中に沈んでいても、花だけは水面上に咲かせる種類があります。これはかつての陸上生活の名残です。水草は陸上の植物が水中生活に適応して進化したものと考えられています。

植生豊かなため池

水面上に花を咲かせるミズオオバコ
ため池の水草の適応
水草の中には、水が引いて干上がっても陸生形を形成して生き延びる種類があります。陸生形は、ため池のように水位が下がる環境で生きる水草にとっては重要な適応です。
水中と空気中でまったく形の異なる葉(異形葉)を展開する性質も、興味深い適応です。このような性質を持っているからこそ、水位変動の激しいため池で生きることができるのでしょう。
その他にも水草には興味深いさまざまな適応が見られます。雄花を水面に漂わせ、水面で受粉するセキショウモの花はその一例です。

キクモの気中葉(左) 水中葉(右)

ヒルムシロの陸生形

セキショウモの受粉水面に 浮いているのが雄花
秋から冬にかけて、多くの水草がさまざまな形をした越冬芽(殖芽と呼びます)を形成します。食用にするクワイやレンコンも、殖芽の1種です。冬季には管理や改修工事のために池の水が抜かれることがありますが、乾燥や低温に耐えることができる殖芽の形成によって、冬を無事に乗り越えることができるのです。

クワイの殖芽

ガガブタの殖芽
平野部のため池の水草
平野部にあるため池は、まわりを堤防に囲まれた皿池で、水深は浅く水質は富栄養化が進んでいます。このような池の周囲にはヨシ、マコモ、ヒメガマなどの大型抽水植物が群落を形成し、水面はヒシ、オニビシ、オニバスなどの浮葉植物がおおっています。外来種のホテイアオイや絶滅危惧種のサンショウモが群生している池もあります。東播磨地域は、絶滅が危惧されているオニバスの全国有数の多産地として知られています。

平野部で見られる皿池

オオトリゲモ

サンショウモ
丘陵地や山間部のため池の水草
丘陵部や山間部には、谷をせき止めて築かれた谷池が数多く見られます。水質は貧栄養~中栄養です。林に囲まれた池は、たくさんの落ち葉が入るために水の色が褐色をした腐植栄養と呼ばれる水質になっています。
貧栄養~腐植栄養の水質の池に典型的な水草はジュンサイ、ヒツジグサ、フトヒルムシロです。水中にイヌタヌキモが漂い、水底にはミズニラが生育していることもあります。

丘陵地で見られる谷池

ヒツジグサ
中栄養のため池になるとガガブタやヒルムシロが優占してきます。ノタヌキモの黄色い花が水面を染めるのもこのような池です。セキショウモやクロモなどの沈水植物が多産し、種の多様性が高くなるのも中栄養の池です。

ガガブタ

ノタヌキモの花
水草と人間の暮らし
水草の中には、人間の暮らしと密接にかかわってきた種類があります。例えばヒシはもっとも普通に見られる水草ですが、飢饉の際の救荒植物として利用されたために広がったと思われます。若芽を食用にするジュンサイ採りも播磨地方では盛んに行われていました。しかし、最近は水質の悪化により良質なジュンサイが採れる池は少なくなっています。人間の生活とは関係のないように見える水草も、さまざまな生きものの生活基盤を提供したり、水辺の景観を構成する上で大切な役割を果たしています。

ジュンサイ

食用にされるジュンサイの若芽